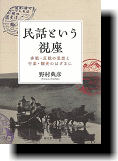 戦蹟や伝説の地を巡る戦前の旅行や「ディスカバー・ジャパン」など、観光の中の「語り」。あるいは、トルストイ伯爵のヤースナヤ・ポリャーナ邸に始まる「民話」の受容、そして、農民文学運動、国民的歴史学運動との関連。柳田国男や関敬吾、宮本常一、野村純一、瀬川拓男、松谷みよ子ほか、民俗学者・児童文学者における「民話」、「昔話」「伝説」。それらを通じ、「民話」や「語り」の意味の変容をたどる。
戦蹟や伝説の地を巡る戦前の旅行や「ディスカバー・ジャパン」など、観光の中の「語り」。あるいは、トルストイ伯爵のヤースナヤ・ポリャーナ邸に始まる「民話」の受容、そして、農民文学運動、国民的歴史学運動との関連。柳田国男や関敬吾、宮本常一、野村純一、瀬川拓男、松谷みよ子ほか、民俗学者・児童文学者における「民話」、「昔話」「伝説」。それらを通じ、「民話」や「語り」の意味の変容をたどる。■本書の構成
はじめに
第一章 《神話・伝説》の時代の日本人の旅、そして口承文芸
序 説
第一節 一九三〇年頃、《神話・伝説》と帝国
第二節 瀬戸内の風景、あるいは満洲の風景
第三節 船旅と「語り」 ―案内人とマリンガール―
第四節 「鮮満」の名所
第五節 戦蹟の語り ―案内人―
むすびとして 日露戦争、満洲事変と私たち
第二章 「民話」の思想、「民話」の受容
序 説
第一節 大正・昭和初期の「民話」とその思想
第二節 「民話=昔話」観の消滅
第三節 柳田国男の旅、「民俗学」以前
第四節 瀬川拓男と松谷みよ子の「民話」
第三章 「民話のふるさと」ともうひとつの〈民話〉
序 説
第一節 『忘れられた日本人』という「民話」
第二節 《昔話・伝説》研究と「民話のふるさと」
第三節 詩と民話の旅、震災の「伝承」
初出一覧
あとがき
索引
野村典彦(のむら のりひこ)…………1965年生 千葉大学等非常勤講
本書の関連書籍
野村純一著作集 全九巻
◎おしらせ◎
『日本文学』第75巻第1号(2026年1月)に書評が掲載されました。 評者 高木史人氏
民話の百年を総括する好著
神話や伝説という言葉が世の中に浮かび上がってくるのは、台湾や朝鮮・満洲に植民地を拡大する時代だった。船や鉄道というインフラが整備されると、人々は瀬戸内海で鬼ヶ島伝説を聞き、大陸に渡って日露戦争や満洲事変の戦蹟を巡った。内地・外地に新たな名所が次々に生まれ、蒐印帖にスタンプを押しながら聖地巡礼をしたのである。柳田国男が民俗学を確立し、その中に口承文芸を位置づけたのは、そんな雰囲気から距離を取ることだった。
それは、民話という言葉が次第に頭をもたげてくる時代でもあった。早い例はロシアのトルストイの翻訳に見られ、農民文学運動に受け継がれ、戦後は木下順二の『夕鶴』に始まる民話運動に展開した。だが、柳田国男は、書き手が思想を盛り込む民話の台頭をひどく嫌った。そのため、昔話の国際比較を進めた関敬吾は、民俗学との折り合いをつけようと奮闘した。一方、説話文学に関心を寄せる益田勝実は、話型をあてはめる研究を批判した。木下の意志を受け継いだ松谷みよ子は、文明化の中で生まれた現代の民話を集めた。
そうした動きは、農山漁村を歩いても、なかなか昔話を聞くことができなくなった民俗学者の動きを刺激した。宮本常一の『忘れられた日本人』がまず雑誌『民話』に連載されたのは、それを象徴する。昔話研究に飽き足らない民俗学者の中には、柳田が提唱した世間話研究に向かい、民話研究と連動してゆく場合もあった。それが「目前の出来事」「現在の事実」を書いた『遠野物語』の再評価の時期と重なったのは、偶然ではない。ディスカバージャパンと呼ばれた観光振興にあおられて、民話は一大ブームになった。
著者が描いた見取り図は、だいたいこんなことになろうか。今、民話は昔話・伝説・世間話の総称のように言われるが、こうして百年を見渡すと、反戦と観光のはざまを揺らいでいて、口承文芸の一ジャンルと見ることは難しい。本書は、そうしたことを論証をするために、豊富な図版や丁寧な地図を載せるだけでなく、雑誌や新聞の初出に戻って文章を読み解いた。そうした細部のニュアンスは、やはり本書を読んで理解していただくしかない。多くの方に本書をお薦めするゆえんである。